多くの人はアジャイルマニフェストを思い浮かべると、すぐに4つの価値や12の原則を思い出します。
しかし、実はその前に書かれている一文こそが最も力強いのではないでしょうか。
「私たちは、ソフトウェア開発の実践
あるいは実践を手助けをする活動を通じて、
よりよい開発方法を見つけだそうとしている。」
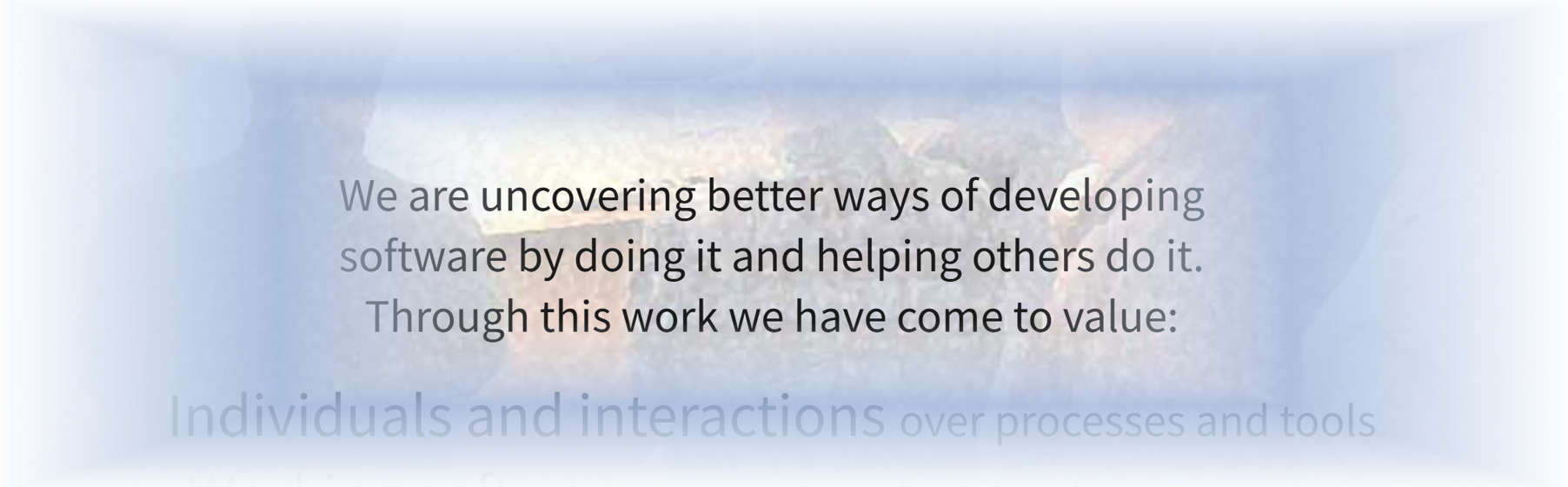
この一文には、2001年に集まった17人の探検者たちのマインドセットが現れています。彼らは絶対的な戒律を書いたわけではなく、複雑さに対する謙虚さと好奇心に突き動かされていました。ソフトウェア開発を、実験と学習と共有によって進化させる「動きのある領域」として見ていたのです。
価値観や原則そのものも重要ですが、その背後にあるマインドセットを忘れてしまえば、私たちはすぐに惰性に流されてしまいます。
「ベストプラクティス」という罠
今日のアジャイルコミュニティにおいて、この探求の精神が必ずしも生きているとは言い切れない気がします。多くの場合、私たちは「ベストプラクティス」という便利なレシピ集に頼りすぎ、人々が自律的に学びながら前進する機会を奪ってしまいます。
ユーザーストーリー、デイリースクラム、インパクトマッピングなどは、状況次第で大きな価値を生みます。しかしこれらの技法はあくまで『グッドプラクティス』であり、どこでも通用する『ベストプラクティス』ではありません。そう呼んでしまった瞬間に、好奇心は閉ざされてしまいます。
顧客に価値を届けること、プロダクトマーケットフィットを見つけること、そして人々を組織化すること―いずれも複雑な問題です。複雑な問題は、処方箋的なやり方では解けません。必要なのは経験主義です。すなわち、仮説を立て、実験し、結果を振り返り、次の一歩を決めること。
だからこそアジャイル開発は「反復増加型」であり、だからこそスプリントがあり、顧客と早期に・頻繁に対話するのです。
同じマインドセットは、プロダクト開発だけではなく、チームや組織の運営にも適用できるはずです。しかし多くの組織は、一度フレームワーク(Scrum、SAFe、LeSS、XP、OKR、いわゆるSpotifyモデルなど)を導入すると、それに執着してしまい、組織のあり方を実験しなくなってしまいます。
あなたのチーム、あるいは組織全体で最後に「働き方をより良くするための実験」を意図的に行ったのはいつでしょうか?
以下の2つの実例が、どのように実験できるのか、そしてどんな学びが得られるのかを示しています。
ストーリー #1:スクラムをやめてみる実験
私が支援していたソフトウェアプロダクトチームは、3年以上にわたってスクラムを使っていました。スクラムは当たり前のように機能しており、誰もが「うまくいっている」と思っていました。
ある大きなリリースの直後、ユーザーからの問い合わせや改善要求が多発することを予想していたタイミングでのスプリントレトロスペクティブにて、一人の開発者がこう言いました。
「今はスプリントをやる必要はないんじゃないでしょうか? 一旦スクラムをやめて、目の前の出来事に集中した方がいいと思います。」
チームは「リスクも低いし、合理的だ」と合意し、4週間ほど「カンバン」に近いスタイルで動くことにしました。
4週間後に振り返ると、ユーザーからの問い合わせは落ち着きを見せましたが、予想外の気づきもありました。
「スプリントゴールがあると、毎日自分のベストを尽くしたいと思える。実はゴールがないことが物足りなかったんです。」
チームはスクラムを再開することを決め、以前よりも強くスプリントゴールを意識するようになりました。
このプロセスはとてもシンプルです。
- 仮説を立てる:「今はスクラムをやめた方がうまくいくのでは?」
- 実験する:「スプリントをやめてみる」
- 結果を振り返る:「スプリントゴールの存在がやはり必要だと実感した」
次を決める:「スプリントゴールをより重視してスクラムを再開する」
ストーリー #2:チーム構造の実験
私が支援していたある製薬会社の営業・マーケティング部門では、10人規模のクロスファンクショナルチームを各地域に設置し、それぞれに「リーダー」を置いて活動していました。1年間安定して運営されており、全体としてはうまく機能しているように見えました。
ある時、部門長は複数チームに共通する課題を見つけました。そこで、新しい実験を仕掛けました。地域横断で5人を選び、期間限定のチームを作ったのです。ミッションは与えましたが、リーダーは置かず、チーム自身が具体的な目標を決めて進める形を取りました。
数スプリント後、チームは目標を達成し、解散しました。その振り返りでは3つの学びが得られました。
- 期間限定のチームは有効であり、大きな混乱を招かない。
- 10人よりも5人の方が、アイデア探索や意思決定においてはるかに効果的。
- リーダー不在の方が、メンバーのオーナーシップが高まり、結果的に成果も出やすい。
この学びを受け、部門長は全てのチームを2つに分割し、小規模チームに再編成しました。
プロセスはやはり同じです。
- 仮説を立てる
- 実験する
- 結果を振り返る
- 次を決める
プロダクト開発を超えた経験主義
チームや組織の「最適な働き方」を見つけることは、顧客に価値あるプロダクトを届けることと同じくらい複雑です。だからこそ、経験主義はプロダクト開発だけでなく、組織運営にも適用できるのです。
逆に「ベストプラクティス」やフレームワークに固執してしまうと、好奇心は閉ざされ、実験が行われず、改善も止まってしまいます。
アジャイルマニフェストの最初の一文は、こう語りかけていると私は思います。「アジャイル開発」は完成したレシピではなく、探求のマインドセットなのだ、と。
「私たちは、今でもよりよい方法を見つけ続けている。自分たちで実践し、他の人々を手助けをしながら。」
それでは、あなたのチームが次に挑戦する実験は何でしょうか?
ー

グレゴリ・フォンテーヌは、Scrum.orgの約350名のプロフェッショナルスクラムトレーナー™(PST)の一人で、合同会社AgoraxのCEOです。ソフトウエア開発だけでなく、さまざまな分野でスクラムを適用してきた長年の経験を持ち、日本における最初の日本語対応プロフェッショナルスクラムトレーナーとして、長年にわたり日本のクライアントや受講生をサポートしてきました。
